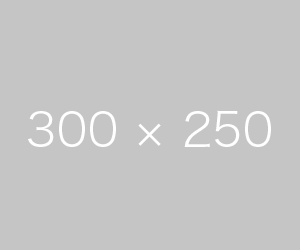・沖縄の黒糖は、1623年に儀間真常(ぎましんじょう)が中国から製糖技術を学び持ち帰ったことに始まり、以後、琉球王国の重要な基幹産業となり、文化・経済・食生活に深く根付いてきた。
・江戸・薩摩藩の専売制度や「貢糖」といった税や年貢の納入形態で黒糖が政治・財政の道具ともなった時期があり、その過程で生産者や地域社会に大きな影響を与えた。
・現代では、黒糖生産は沖縄の離島を中心に「伝統・味・地域ブランド」として再評価されており、製造数・生産地が減少しながらも、文化としての価値が高められている。
このような人に読んでほしい記事です:
・沖縄・琉球文化や伝統産業としての黒糖に興味がある方
・黒糖を単なる甘味料以上の「歴史・文化的価値」として理解したい方
・食・産業・社会の視点から黒糖の歩みを知ることで、今後どう保護・発展させていくべきか考えたい方
歴史の流れとポイント
・黒糖が琉球王府の専売財産となる → 経済的・政治的な重要性を持つようになる
・奄美群島・薩摩の関与、貢糖制度、黒糖地獄と呼ばれる状況の発生
・近代化・殖産興業期以降の農政・作付け制限・増産努力・政策的変化
・戦後・現代における生産の縮小・工場数の減少・離島でのブランド化・持続可能性の問題
黒糖の起源と琉球王朝への導入(17世紀〜)
黒糖が琉球で製造され始めたのは、1623年(元和9年)と言われています。儀間真常という琉球の士族が中国・福州へ使者を送り、そこで製糖技術を学ばせ、それを琉球にもたらしました。
この導入により、さとうきびの栽培が本格化し、黒糖は島の主要農作物となりました。琉球特有の気候(亜熱帯・サトウキビ栽培に適した環境)がその普及を後押ししました。
黒糖の専売制度と貢糖・薩摩藩の影響
江戸時代になると、沖縄(琉球王国)は薩摩藩の支配下に置かれ、黒糖は年貢・貢物(貢糖)として薩摩藩に多く納められる対象となりました。特に 18世紀前半には、米の代わりに黒糖が納税材とされることもあり、農民にとって重い負担となることがありました。
奄美群島でも同様の制度が敷かれ、「黒糖地獄」と呼ばれるほど、黒糖生産のための労働・税負担が過酷だったという記録があります。農民は自分たちの食料を確保しながら黒糖を栽培・製造しなければならず、生活に深刻な影響をもたらしました。
明治以降の変化・近代化
明治政府の成立後、琉球は沖縄県となり、日本の行政・税制度に編入されることで、黒糖産業の扱いも変化します。作付け制限や糖業改良・設備の近代化など、政策的な支援と制約の両方がありました。
また、20世紀半ば以降、材料や生産技術の機械化、大型工場化などが進む一方で、伝統的な小規模工場・離島での黒糖生産は次第に減少していきます。特に1970年代以降、黒糖を作る工場の数は大幅に減りました。
戦後から現代:ブランド化と文化の再評価
戦後、日本の経済成長とともに、砂糖全体・精製糖産業が拡大する中で、黒糖はその風味・伝統性ゆえに市場のニッチを形成してきました。沖縄では、八つの離島(伊平屋・伊江・粟国・多良間・小浜・西表・波照間・与那国)が黒糖の生産地として残り、それぞれの島で土壌・気候・製法の差が味に表れており、「島ブランド」「伝統食品」として価値が高まっています。
現在、沖縄県の耕地の約半分がサトウキビ栽培に使われている一方で、そのうちのごく一部(5~6%程度)が黒糖生産に使われており、黒糖は希少性のある甘味料となっています。
伝統的な呼び名として、黒糖は「ヌチグスイ(命の薬)」と呼ばれることもあり、健康・薬用食としての評価を持っていたことも歴史文献に見られます。